
ヒマラヤ山脈で約6億年前の海水を発見、カンブリア大爆発と関連か 新潟大...
新潟大学は8日、インド理科大学院大学との共同研究で、ヒマラヤ山脈の高地で炭酸塩鉱物に閉じ込められた約6億年前の海水を発見したと発...
東北大学理学部物理学科修士課程修了。ソフトウェア技術者。情報機器・教育機器の開発に長年従事し、近年は自動車エレクトロニクスやIoTに関わる。得意分野は本業の技術系。絶滅危惧種、環境問題などもカバー範囲。

新潟大学は8日、インド理科大学院大学との共同研究で、ヒマラヤ山脈の高地で炭酸塩鉱物に閉じ込められた約6億年前の海水を発見したと発...
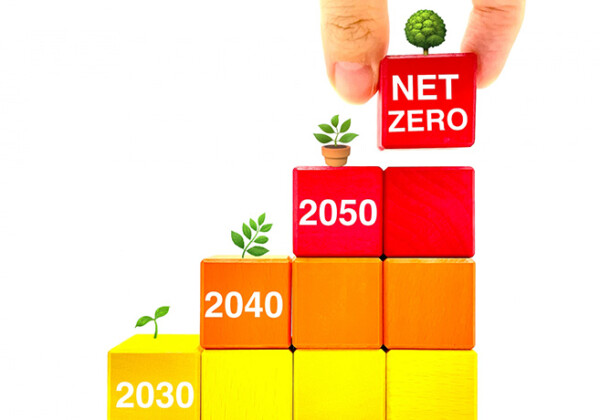
京都大学は2日、さまざまなガス分子の中から二酸化炭素(CO2)に対してのみゲートを開いて吸着するフレキシブル多孔性材料の開発に成...
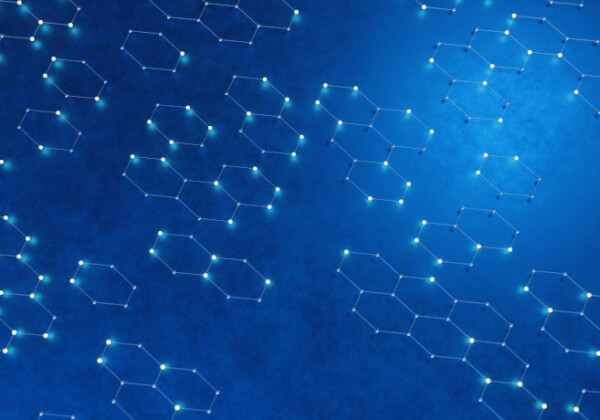
東京工業大学は7月28日、貴金属を使わずに、水に安定でかつ高性能なアンモニア分解触媒を開発したと発表した。既存の触媒に比べてアン...

東北大学は20日、宮古諸島に生息する固有種の起源は沖縄本島と宮古諸島の間にかつて存在し現在は水没した陸地だという仮説を発表した。...

東京農工大学と山梨県富士山科学研究所の研究グループは12日、シカとカモシカの直接的な交渉を8年間直接観察、シカからカモシカへの攻...

立命館大学は6日、生態系の再生のために日本の野山にオオカミを再導入するべきかについて1万人を対象とした大規模な意識調査を行ったと...

大阪大学はCO2をメタン(CH4)にほぼ100%変換できる金属製自己触媒反応器を作成したと発表した。新しい触媒の作成技術によって...

東京大学と北海道大学は22日、北海道北部の旧北海道帝国大学演習林の調査データから、近年の気候変動や森林伐採の影響を受ける以前の約...

国立環境研究所と海洋研究開発機構は16日、アジア地域の地表から排出されるメタンを、物質循環モデルや排出イベントリに基づくボトムア...

国立科学博物館と東京都立大学は9日、自動車排ガス浄化触媒の耐久性を劇的に向上させる触媒調製手法を開発したと発表した。新手法による...

山形大学は日本IBMと共同で、AIの深層学習技術を利用して航空写真からナスカの地上絵を発見する手法を確立し、新たな地上絵を4つ発...

九州大学は26日、有機ELよりも単純な構造で1000時間以上の寿命を示す電気化学発光セル(LEC)を開発したと発表した。さらなる...

早稲田大学は19日、繰り返して充放電できる全固体空気二次電池を開発したと発表した。小型軽量で液漏れや発火の危険性がなく折り曲げて...

大阪大学と奈良先端科学技術大学院大学の研究グループは、レーザー照射により狙った時間・場所に様々な形状の氷結晶を発生させる技術を開...
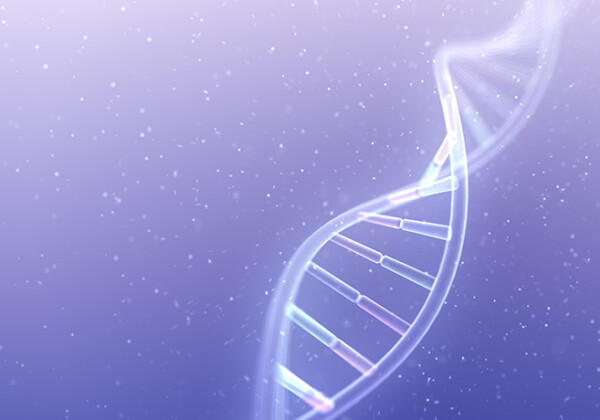
遺伝を司る基本物質DNA(デオキシリボ核酸)の二重螺旋モデルは、ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックの二人の研究者によって...

東北大学は4月27日、レアメタルを用いないで従来よりも大容量で高電圧の空気電池を開発したと発表した。空気電池の電圧と出力を高めた...

中央大学、新潟大学、国立環境研究所は18日、絶滅危惧種ムジナモの自生個体群が石川県内の農業用ため池において発見されたと発表した。...
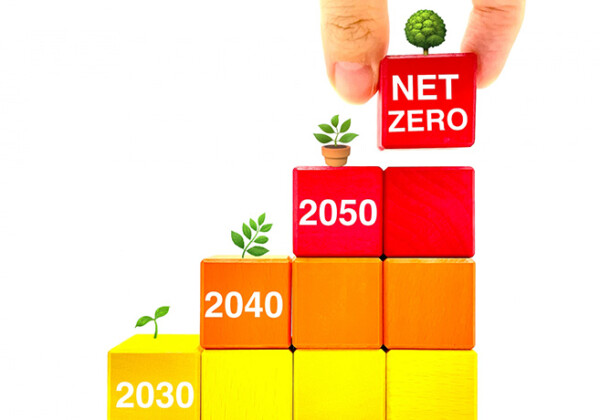
東京工業大学(以下、東工大)は11日、パラジウム(Pd)とモリブデン(Mo)の金属間化合物触媒を用いて、8.9気圧と25℃という...

森林研究・整備機構 森林総合研究所と福島大学は7日、野外に生育する樹木においてDNAの突然変異を迅速に検出する方法を開発し、福島...

信州大学は3月31日、環境中の微小なマイクロプラスチックを回収するデバイスを開発し、従来の濃度の百倍で回収することに成功したと発...

大阪公立大学は23日、海水や温泉水などの環境水中に微量存在するレアアースを、リン酸基を付加したパン酵母を用いて回収することに成功...
